南海トラフ地震が来るという話はもう何回となく耳にされているかと思いますが、実際に来たらと思うと本当に怖いですよね。
みなさんは自分が住んでいるところはどの程度の揺れになるかとか、把握しておられるでしょうか?そのためにはまず、今までその土地で起こった地震の歴史を調べないといけません。歴史は繰り返します。断層や揺れについて知っておくことは無駄ではないと思われます。
そしてこのブログは京都に関わる話題を取り上げていることから、今回は今まで京都で起こった地震の歴史を掘り下げてみることにしました。京都に起こる未来の地震を想定するため、過去の地震を検証します。
そしてその結果、注目するべき点があることに気が付きました。それも最後にみなさんにお伝えしますので、是非最後まで目を通してくださいね!
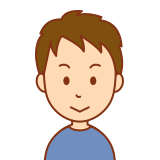
有名なお寺や神社もすごい揺れに遭ってるんだろうね。

それがこれから「いつか必ず起こる」のん。覚悟しとかんとなぁ。
また別の記事では、実際に地震が起こったときの京都の状況を書いてます♪
京都で被災した場合の、いざという時のお役立ちリンクも揃っています♪
ではでは、「京都の地震の歴史」を振り返ってみましょう。
1.京都の大地震の歴史
①京都で起こった主な大地震
「京都であった大地震」と言っても、すぐには思い浮かべることはできません。しかし実際は本当に何度も何度も起こっています。京都に直接関係のあった地震だけでも並べてみたら、こんなになりました。
| 年 | マグニチュード | 地震名 | 地震の要約 |
|---|---|---|---|
| 827年 | M6.8 | 京都地震 | 平安時代の記録に残る最古級の大地震。 家屋が多数倒壊し、余震は翌年6月まで続いた。 |
| 887年 | M7.9 | 仁和地震(南海トラフ地震) | 津波被害が五畿七道に及び、京都でも圧死者が多数発生。 |
| 938年 | M7.0 | 天慶地震 | 宮中で4名死亡、寺院にも多くの被害。 |
| 976年 | M6.7 | 天延地震 | 家屋の全壊が相次ぎ、死者50名以上。 |
| 1185年 | M7.4 | 元暦京都地震 | 岡崎地区の法勝寺など大寺院群が壊滅的被害。市中でも多くの家屋倒壊・死傷者多数。地割れや液状化も発生。余震3か月。 |
| 1317年 | M6.8 | 京都地震 | 強い揺れと余震が多く、群発地震とも。清水寺が出火。 |
| 1449年 | M6.1 | 文安地震 | 洛中に大きな被害、死者多数。 |
| 1596年 | M7.5 | 慶長伏見地震 | 伏見城天守崩壊、二の丸で女房300人余、城下町で1000人余死亡。京都市街地でも甚大な被害。 |
| 1662年 | M7.6 | 寛文近江・若狭地震 | 京都市中で町屋や屋敷の倒壊1,000軒余、死者200人余。五条大橋崩落、清水寺・八坂神社なども被害。余震1か月半。 |
| 1830年 | M6.5±0.2 | 文政京都地震 | 京都市街地を中心に大被害。二条城や御所の石垣・塀が崩壊、町人街で土蔵倒壊。死者280人、負傷者1300人。 |
震度については、マグニチュードや被害の状況からどれも大地震であったことはわかるので、少なくとも震度5は下らないのではないかと推測されます。
京都の地震被害は南海トラフ大地震と直下型地震によるものです。全部が木造家屋だったこともあり、多くの家屋が倒壊していますね。ただ、1361年の正平地震(M8.4)と1707年の宝永地震(M8.9)は南海トラフ地震だったけれども、それほどの被害がなかったのか、京都の被害の記録を見つけることができませんでした。大きな被害は直下型地震に偏っているように見えます。

この前の戦争中にあった南海トラフ地震の話も、両親は何にも言うてへんかった。軽かったんかな?
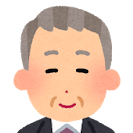
京都の最大震度は5ぐらいだったようですよ。
京都では南海トラフ地震のいくつかは、沿岸部ほど大きな被害が出なかったのかもしれません。1つだけ言えるのは、京都には津波が来ないということ。ここは大きいと思います。しかし油断は禁物。未来はいつも過去の通りにはなりません。被害がゼロになると思ってはいけないでしょう。
*参照:京都旅屋、京都府「南海トラフ巨大地震に係る市町村別被害想定について」、ウィキペディア「京都地震」、「元暦二年七月九日(1185 年 8 月 6 日)の京都地震について」、「第5章 京都での被害と震災対応」
②清水寺が燃え、伏見城が倒壊!
これらの中では、有名な建造物に大きな被害をもたらした地震があります。1317年の地震では揺れが強くその数も多い中で、あの清水寺が炎上しています。
また1596年の安土桃山時代の慶長伏見地震では伏見城が倒壊しました。そこには豊臣秀吉が被害に遭った時の、こんな記録が残っています。
9月の初め、地震はまだ暑い真夜中に起きた。秀吉は裸で寝ていたが、グラッと揺れた時「これは危ない」と身の危険を感じ、傍らの秀頼を抱きかかえ外へ走り出た。そしてその直後、伏見城はほぼすべて崩壊してしまったのだった…
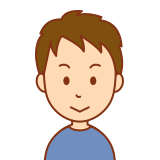
秀吉はよく助かったよね! やっぱり運が強いのかなw

そうとも言えるけど、この地震が太閤さんの天下を終わらせた、て言う人もいやはるえ。
*災害時の常備品。温めなくても食べられる非常食です。うちにも備えています。
2.直下型地震を起こす断層帯はどこにある?
では、京都にはどこに、そしていくつ断層帯があるのでしょうか?直下型地震は活断層で起こり、複数の活断層が帯状にあるところが断層帯と言われます。それを知ることで地震が起こる場所・規模を推定できるので、簡単に位置を見てみましょう。
しかし今回調べてみて、想像以上の数があり驚きました。これが1つでも動いたら大地震が起きるのに、こんなにもあったら京都にもメチャクチャ地震が起こってしまいます。本当に怖くなってしまいましたね。

1か所、2つの断層を一本線で表しています。
京都府近辺には22の断層があり、以下のような断層が有名です。
花折断層帯
奈良盆地東縁断層帯(京都盆地−奈良盆地断層帯南部)
京都西山断層帯(三峠・京都西山断層帯)
木津川断層帯
有馬–高槻断層帯、および生駒断層帯
三峠断層など京都西部の断層群
花折断層帯は京都市の上からまっすぐ降りてきている断層帯です。中心部まで揺れる、これが一番怖いですね。
京都市に限っても周りに15ほどの断層帯が集まっています。京都盆地は断層帯によって作られたことがわかりますね。
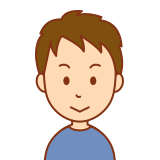
でも、この断層帯が動く確率はすっごく低いそうだよ。

そやけど、これだけ断層帯に囲まれてると思うだけで「ちゃんと準備せな!」て思わへん?
確率は低くても昔動いた断層帯もあります。そして南海トラフ地震は30年のうちに80%の確率で来ると言われています。準備はしすぎることはありません。どの地方に住んでいる方も、是非少しずつでも準備をして行っていただきたいです!
*トイレ対策は必須!まとめて買ってしまうほうが使い方にも困ることはないでしょう。私も買いました♪
3.未来の防災のため、注目しておくべきたった1つのこと。
大地震の歴史を見て来て、1つ注目しておくことがあります。それは
京都では、1830年の文政京都地震以来、200年近く大地震が起こっていない。
ということです。
現在建っている京町家はほとんどがこの地震以降に建てられたものです。大地震に耐えられるか、本当のところよくわかりません。
そして、ここに住む京都の人たちも、大地震を経験した人は誰もいません。なので、京都で良く言われるのが
京都には大地震が起きない
という都市伝説的な噂です。

上京区でも「地盤が堅いし大丈夫」てよう聞くえ。私もちょっとだけそう思てる^^;
京都の人には「京都で地震が起きてもたいしたことない」という変な自信があるんです。大地震の表をあげた時、ちょこっとだけこの自信が顔をのぞかせたところがあるの、わかりました?この安心感が対策に影響しないよう、十分気を付けて対応するべきだなと思っています。
4.まとめ
・京都の大地震の歴史
京都は地震が少ないと思われていますが、実際歴史を紐解くと、非常に多くの大地震が起きていました。
地震により清水寺が炎上したり、伏見城が倒壊し豊臣秀吉が被災した記録が残っています。
京都で感じられた地震には直下型地震と南海トラフ地震がありますが、大きな被害をもたらしたのは主に直下型被害から免れていると言えます。
・直下型地震を起こす断層帯はどこにある?
京都には22の断層帯があり、京都市の周りに限って言えば15の断層帯が存在しています。
これらが動いて地震が起こる確率は南海トラフ地震よりもかなり低いです。しかし数が多いので、どれか1つが動いても大地震になるわけですから、決して油断してはいけないでしょう。
・未来の防災のため、注目しておくべきたった1つのこと。
京都では、1830年の文政京都地震以来200年近く大地震が起こっていません。今住む人に大地震を経験した人がいないせいか、「京都に大地震は起きない」「京都に地震が起こっても大丈夫」という変な自信があります。これが地震対策に影響ないよう気を付けなければいけません。
いかがでしたでしょうか?京都も決して地震の聖域ではない、ということが分かったと思います。どの地方に住んでいても準備は必要ですね!
これが皆さんの地震の準備のお役に立てれば嬉しいです。












コメント